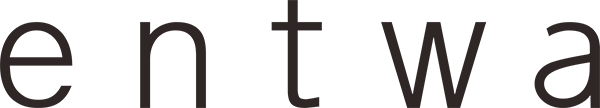風の栖ができてから20年。
「この空間に気持ちいい風が吹いてほしい」という思いから、店主 村上はお店を開きました。
最初はセレクトした洋服、雑貨やカフェからはじめ、やがてNAOTの靴が中心になってきました。NAOTは5年前に店舗として独立。それと同時に、オリジナルの洋服を本格的に作り出して、少しずつではありますが新しい風の栖のことを知ってもらえる機会も増えてきました。
そこでこのタイミングでもう一度、基本に立ち返りたい。
風の栖として大切にしたいことや伝えていきたいことを再確認しよう。
そんな動機から始まったのがこの新連載、作り手 村上が語る「根っこの思い」です。
第1回目は、洋服作りのきっかけの話。
それでは連載スタートです。
***
私が洋服を作るようになったきっかけは、母や祖母の影響が大きいです。
子供の頃、私の洋服はほとんど母の手作りでした。
女学校時代に裁縫の授業がしっかりあったと聞いてます。
それに、戦後の物資が少ない時代は、親が子どもの洋服を作り、おさがりを着るのが当たり前のことでした。
母は、いろいろ工夫して、素敵なギャザースカートや、フリルの付いたブラウスを縫ってくれました。
それを着ていると、豊かな気持ちで満たされたのを今でも覚えていますし、その時に出た「はぎれ」は私の宝物で、それを寄せ集めて人形の洋服を作っていました。私の布好きはここから来ていますね。

また、さらに私の祖母も裁縫が上手でした。
明治生まれで、大変な働きもの。座っていたのは洗濯物をたたんでいるときと、縫い物をしているときだけだったと記憶しています。
その中でもとくに覚えているのが、きちんと整理された祖母の「裁縫箱」です。
きれいな布が貼って作られた裁縫箱の中の赤い指ぬき。
紫色の綿入りの裁ちばさみ袋。黒い糸切りばさみ、丁寧に巻かれた木綿糸。
無くなってもすぐ分かるように、決まった本数しか刺されてない赤い鹿の子模様の針山..。
私は祖母の裁縫箱を見るのが大好きでした。
その中に入っていた「作りかけのぞうきんやふきん」は今でも記憶の中に残っています。
このぞうきんやふきんは、色とりどりの糸で縫われているのですが、それは、中途半端に残った糸を最後まで使うためにつなぎ合わせて少しずつ作っていたのでした。
残り10cmの糸も無駄にしないで、少しずつ縫って仕上げていく..。
幼い私は、その祖母の生き方が普通のことだと思いながらずっと見てきましたし、当時の日本人には、ものを大切にする生活があったのです。
そんな私もまた、娘たちの洋服を手作りしてきました。
今は何でも手に入る贅沢な時代に生きていますが、私はずっと手仕事の、 “オンリーワン” を求めてきました。
欲しい布や色が無いなら作ればいい。作ろう!(これは、母や、祖母から受け継いた思考回路ですね)
染色や手織りを学び、楽しみましたし、糸も布も、そこから自分のものにしていきました。
これが私にとって、ものづくりの原点です。

だからなのか、織屋さんへ行っても「傷がある生地」があると惹かれてしまうんですね。たいてい店主は、「傷があって売れない..」と嘆いているのですが、私にとっては宝物。傷そのものがアートなんです。それをどう生かすか….考えるとワクワクしてきます。
ただ、お店に出す服はオリジナルではあっても、日常に着られるものでなければ..と思っています。
動きやすくて、家で扱いやすい。シンプルなデザインだけど、どこか遊び心があるものがいい。手持ちのものと合わせられたらもっと良い。
絵を描き、パターンをおこしながら考え、何度も試作します。
きっとこれらも全て、工夫して作ってくれた母や祖母から受け継いだ影響が大きいと思います。
好きな服を着ているときの満たされた気持ちはもちろんですが、糸もはぎれも無駄にしないで、繕いながら、直しながら、ものを大切にする生き方を楽しむ。
今、私がそれを次世代につないでいく番。
その気持ちを忘れずに、これからも心からときめくものを、スタッフ達と一緒に「あーでも無い。こーでも無い。」と言いながら、笑って、食べて..作り続けていきたいです。

(ムラカミ)
*他の記事はこちら!
vol.2 -風の栖の洋服に込めた思い-
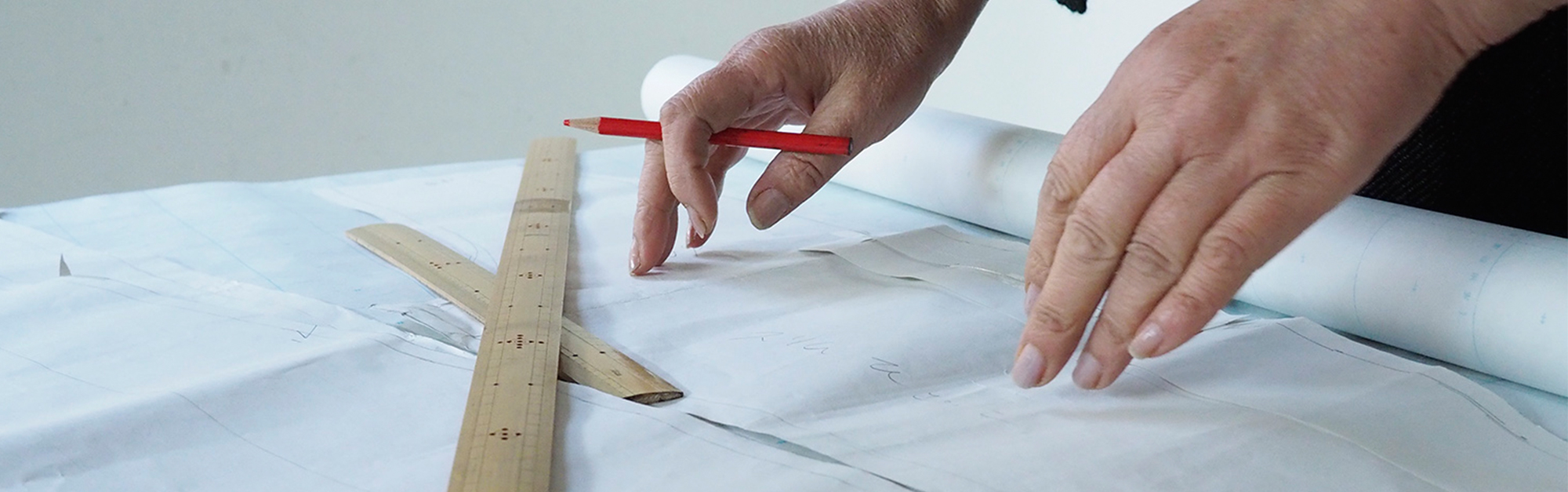
vol.3 -ひざっこパンツの誕生秘話-